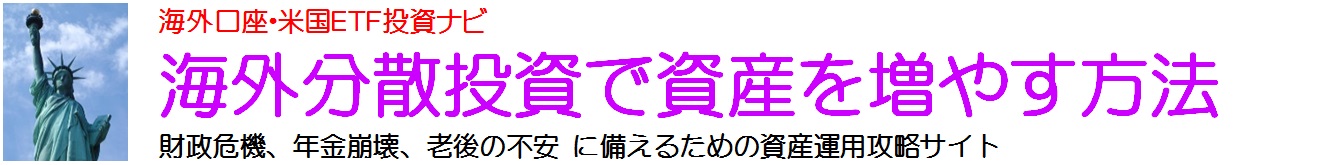経済学は「自らの利益を最大化する合理的な人間」を前提にしていますが、実際私たちの判断は時として当てになりません。
行動経済学とは、そうした「間違いをおこす人間」を前提にして行動を説明する学問です。
行動経済学という学問そのものについて詳しくなることが目的ではありませんが、考え方として資産運用に役立ちそうなものがありましたので紹介します。
|
目 次 1.投資の利益と損失の心理 2.お金の価値が変わる心理 3.損切りできない心理 |
というのも株価にしても為替にしても多くの人間の行動の結果です。また自分自身の行動も合理的とは限りません。感情での行動の方が多いかも。
バフェットの言葉にあるように、投資には辛抱強さと冷静さが重要です。投資に役立つバフェットのことば
行動経済学の考え方は、自分の判断を客観的視点で見るために役立つと思います。
投資の利益と損失の心理
人間が損失と利益をどのように評価するかを説明するのに「プロスペクト理論」というのがあります。
プロスペクト理論は2つの大きな柱があるそうです。
そのひとつが「損失回避性」です。
次のくじを引くとします。
① 必ず20,000円当たるくじ
② 50%の確率で40,000円当たるが、50%の確率で0円のくじ
これは60%の人が①を選んだそうです。
期待値はどちらも20,000円の利益です。
一方次のくじでは、
① 必ず20,000円の罰金のくじ
② 50%の確率で40,000円の罰金、50%の確率で罰金なしのくじ
これは70%の人が②を選んだそうです。
期待値はどちらも20,000円の損失です。
同じ額の利益と損失では、利益のもたらす満足よりも損失のもたらす不満足の方が強く印象に残るというものです。
投資行為では、上昇して儲かっている局面では確実に利益を確保しようとしますが、含み損を抱えた株式は塩漬けにしてしまうという行動も「損失回避性」のあらわれです。
確定利益は小さく、損失は大きくなる投資をした経験はありませんか?
これを繰り返していては儲かりません。
お金の価値が変わる心理
「お金に色はついていません」
これはお金は、
「価値の尺度」(品物の価値を示す)
「交換の媒介」(支払機能を果たす)
「価値の貯蔵」(価値を蓄える)
の機能を持ったモノであるからです。
本来、汗水たらして働いた1万円とパチンコで勝った1万円との間に価値の差はありません。同じ1万円です。
ところが多くの人のお金には色がついています。
出所や使い道によってお金を使い分けています。悪銭身に付かず、あぶく銭などの言葉もあります。
20万円のカーナビを高いと感じる人でも、300万円の新車には簡単に20万円のカーナビをつけます。
更に高額の住宅を購入する時には、普通ではまず買わない住宅に付帯するモノやサービスを簡単に購入しがちです。
行動経済学では、こうした心の働きは「メンタルアカウンティング(心理会計)」と呼ばれます。
株式投資で利益が出ても、あぶく銭となってしまうとお金は増えません。
行動経済学の例から、自分の行動を客観的に見つめると役に立ちます。
損切りできない心理
「サンクコスト(埋没費用)」とは、既に支払われた費用で、何をどう努力してももう回収できない費用を指します。
現在の意思決定は、今後の利益と支出の予想に基づくものであり、サンクコストは一切考慮に入れないことが必要である とビジネスや投資では言われます。
しかし、実際の行動はどうでしょうか?
食べ放題料金を払ったから、満腹で苦しいにもかかわらず食べていませんか?
ビジネスの世界では、新規事業に投資したが思うように成果が出ず、今後も期待できないにもかかわらず延命のために追加融資をして、更に損失を拡大してしまうなんてこともあります。
投資の世界では、株式を買った企業がとんでもないポンコツで株価が下落したにもかかわらず、なかなか売る判断ができない。
身の回りには、支払った金銭的・時間的な損失を割り切れないでいるケースが多くあります。
私の経験では、サンクコストを諦める、つまりは損切りが出来るようになる には繰り返しの練習がいります。
行動経済学の考え方から自分の行動を客観的に見つめると、投資の役に立つのではないでしょうか。
このページの関連記事
●投資の失敗事例から学ぶ
●初めての人のための資産運用ガイド
クリック応援お願いします!記事を書く励みになります。
![]()
![]()
![]()
にほんブログ村